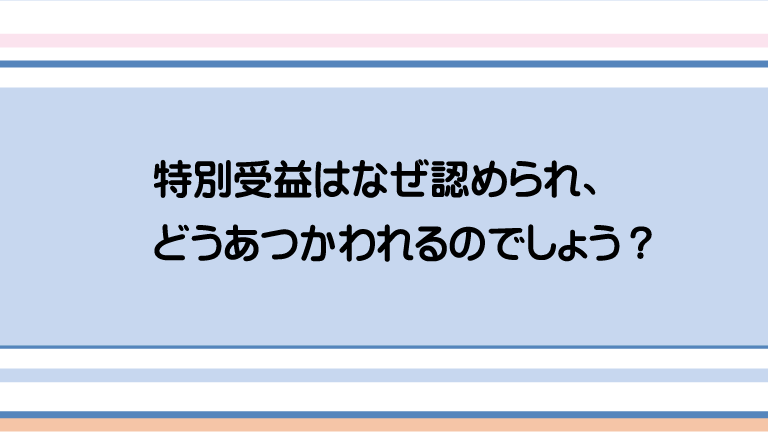Contents
特別受益は、共同相続人間の平等を図るため制度です。
亡くなった方(被相続人)から生前贈与を受けていた人がいる場合、これを特別受益として、遺産分割のときに清算するのです。これは、贈与などを先にしてあるのは、相続分の前渡しであるという考えが基礎になっています。
そうすると、「いや、お父さんがこのマンションを私にくれたのは他の兄弟より多く相続させるつもりであったはず!」という主張をしたい人にはこの制度は不利なものになります。
確かに、ある相続人にたくさんあげたくて贈与したという可能性もありますが、そうであれば遺言を残すことでその点が明らかにできたはずなので、それがなされていない以上、そういうつもりはなく、単に、ある相続人だけに先にあげたにすぎないという考えを、裁判所はしています。この考えを覆すことは、非常に難しいと考えた方がよいでしょう。
特別受益のまとめ:
- 目的:平等にするため
- 方法:特別受益となる贈与などを加えたものを相続財産とみなしてそのみなし相続財産を使って各相続人の相続分を算定していく
- 背景の考え方:被相続人は、先に遺産を渡しておいただけだ、という考えでの清算
このみなし相続財産の相続分から、特別受益を受けている人の受益分を引いて、その残額だけが現実にもらえる相続分にしていきます。
この実際に特別受益者がもらえる相続分を具体的相続分といいます。
弁護士や裁判所は、この特別受益となってすでに贈与で相続財産つまり遺産からはずれている財産を計算上だけですが、足しこんでいくことを「持戻し」と呼んでいます。
多くもらいすぎている相続人はどうするのか?
上記のように計算すると、すでに本来もらえるものよりたくさんの贈与を受けていた人がいることがあります。持戻しをした財産で計算した相続分を超過して、贈与などを受けていた人は、超過分を返還する必要があるのでしょうか?
その必要はないとされています。でも、その相続で新たに財産を取得することはできません(民法903条)。
これは、平等という観点からはおかしいようにも思われますが、そういった人にだけ多額の財産をあげていた亡くなった方(被相続人)の意思解釈(気もち)に合っていると考えられ、また、返還するべきであるとするとすでに財産を自分のものとしている人に対してあまりに不都合です。
しかし、このようなもらいすぎの人が他の相続人の遺留分を侵害するときは、その限度では遺留分減殺請求の対象となります。つまり、遺留分が侵害されているほどであれば戻さないといけないわけです。
特別受益を受けていないひとでどうわける?
特別受益をたくさんもらっているひとがいる場合、他の相続人でどんな風にわけるのか、これは複雑な問題があります。単に、多くもらいすぎてしまってもうもらえない相続人を外して、通常の遺産分割をすればよいのか?という問題です。
例えば、相続として、1億2000万円の遺産を分ける場合を考えましょう。
相続人は妻と子のABCだとします。
Aが生前に3600万円の生前贈与を受けているとします。そして、Cは、遺贈で(不動産を)2400万円分もらっているとします。
みなし相続財産は、相続財産1億2000万円に3600万円の生前贈与を加えたものです。
つまり、1億5600万円です。
そうするとみなし相続財産でわける一応の相続分は、 妻が7800万円で、子らはそれぞれ2600万円となります。
しかし、Aはもらいすぎの部分があって、それが1000万円なのでもうもらえません。
Bはなにももらっていないので、2600万円もらって、Cは遺贈で2400万円もらうので、残りの200万円もらう、
となりますね。
このように考えてわけるとすると、超過特別受益者のAは何ももらえないので、他の三人、妻とBCでわけるのですが、
全体で7800+2600×2
1億3000万円が必要ですが、実際には1億2000万円しかありません。
つまり、誰かがもらいすぎていたために、不足が出てしまうのです。
このとき、どうやって残りで相続財産を分けるのがよいのでしょうか?残念ながら民法は条文を用意していません。 ですので、どう考えるのかということになり、裁判所の実務では大きく分けて二つの考えがあります。
超過した人を抜いて実際の遺産を相続割合で分ける方法
この方法の計算方法としては、そもそも、みなし相続財産は1億2000万円として、それを妻とBCでわけるという方法があります。これでは、妻が6000万円、BCはそれぞれ3000万円になります。Cは遺贈があるので遺贈分2400万と別に600万円もらうというのが、具体的相続分になります。
当初の計算による割合を使うという方法
これに対し、当初の一応の計算による具体的は相続割合を使うという考えもあり、それは、下記のような考えです。
当初の計算では、妻が7800万円、B2600万円、C200万円の比率によって分けるべきとなっていましたね。ですので、その割合を使って現実の相続財産(遺贈分を抜いたもの)を分けるというものです。
現実には、1億2000万円-2400万円という計算で、遺贈を抜くと9600万円が相続財産ですので、それを、全体を7800対2600対200という割合で妻、B、Cがもらうということになります。
その結果の各自の具体的相続分は、甲が7064万円程度、Bが2354万円程度、Cが181万円程度ということになろうかとおもいます。
もっとも、この後者の計算は複雑になりますし、他にもいろいろな意見はあります。
複雑なお話になってしまったのですが、これは、超過した特別受益者がいるけれどその分を戻せと言えないことから、足りなくなっている相続財産・遺産をどう残りで割り付けるかという問題です。
まとめ : 超過特別受益者がいたときの、残りの相続人でのわけかた 大きく分けて二つの考えがある
① 超過受益者はいないものとして、他の相続人間で改めて相続分の算定する方法 (岡山家庭裁判所の審判例 昭和55年 8 月30日) 超過受益者はいないものとして、他
の相続人間で改めて相続分の算定する方法 (岡山家庭裁判所の審判例 昭和55年 8 月30日)
② もらいすぎている超過受益者を除いてから、他の相続人間で、全相続人の相続分の割合で残った相続分を計算するという方法 (大阪家庭裁判所の審判例 昭和51年 2 月16日)
持戻しをしないということができるのか?
先ほど説明していますが、亡くなった方(相続人)は、もしかしたらその人には多めにあげるつもりで先に土地と建物を遺贈していたのかもしれません。でも、相続法ではそのように考えない、先渡しをしただけと考えるのです。
でも、持戻しはしたくないと、被相続人が考えていた場合、その意思を表示しておければ持戻しはしません。民法903条があるのです。
民法をみておこう : 第903条
- 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
- 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
- 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
持戻免除の意思、どうやってこの意思を表示するのでしょう?
生前贈与についての持戻免除の意思表示については遺言でなさなければならないことはありません。
また、書面でなくてもよいので、口頭でそういうことを言っておいてもよいのです。
ですが、書面がないとなかなかその意思があったこと、表示されたことは立証できないでしょうね。
生前贈与がある場合、なにか特別の事情があって、持戻免除の意思表示があったといえるような場合かどうかは、弁護士とよく話し合って過去の証拠や経緯を見直してみるとよいでしょう。
たとえば、共同相続人の1人に贈与がなされているのに、この贈与に言及することない遺言があってそこで、相続分が指定をされているようなとき、持戻免除の意思表示があるという解釈をした審判もあります。東京家庭裁判所の昭和57年3月16日の決、東京高等裁判所平成8年8月26日の決定などです。
遺言の時にはすでに贈与していたわけなので、その後でこの人の相続割合はこうするという決め方を遺言がしたのであれば、持ち戻してしまうとその割合が崩れてしまうので、持戻しはしませんという意思があったという解釈になったのでしょう。合理的な決定だとおもいます。
もし、この意思によって遺留分を侵害されたひとがいた場合、遺留分減殺請求ができますが、それで遺言が無効となることまでは、ないと思われます。
どんな行為が特別受益にされているのでしょう?
特別受益として持戻しの対象となる財産は、上記での民法903条で 遺贈 婚姻、養子縁組のための贈与 生計の資本としての贈与 となっています。
「生計の資本」という言葉が贈与の前についていて限定されていますね。
これは、小遣いとかお見舞金といった少額の贈与まで含めると計算が煩雑となるからということが理由とされています。
どんな贈与(生前贈与)が相続において特別受益になるか?
それが相続財産の前渡しとみられる贈与であるかということを基準として、相続人間の公平を考慮して判断されるべきといわれています。こういう場合は前渡しだという基準がありません。総合的に決定されるべきであるとされているのです。
よって、代理人弁護士は、どこまで特別受益なのかという点は、しっかり調停でも審判でも主張をするべきです。
婚姻・養子縁組のための贈与とはなにか?
持参金や嫁入り道具、結納金などの、婚姻とか養子縁組のために特に被相続人に支出してもらったものがこれです。
結婚式の費用については、どうなるのかは、はっきりしていませんが、あまり高額なものではなく通常のものはこの贈与ではないでしょう。
「生計の資本としての贈与」とは?
典型的なのは、子が購入する不動産の頭金をだしてあげるような場合です。
それから事業のための資金とか土地を贈与した場合も含まれ、金額がかなり多い時(数百万円以上)であれば、特別な事情がない限り、この特別受益となるでしょう。
お小遣いのようなものは特に多くもらっていても、含まれません。生活援助のためのものも、扶養目的なので含まれません。
学費は、大学のための学費をひとりだけが受けたような場合には、特別受益にあたると、解されます。しかし、亡くなった方の財産状況によっては、通常の扶養として学費をだすこともありますので、資産収入及び家庭事情というような事情によっては、大学学費は特別受益とならないこともあります。
生命保険とか死亡退職金をもらった人がいる場合、どうなるのか?
これらは、通常、相続財産には含まれないとされます。
しかし、遺贈と同様の機能を有することがあるので争いになることが多く、せめて、特別受益に準じてこれらの持戻しを考慮すべきではないかということが言われています。
公平を重視して持戻しの対象とするべき場合は多いように思えますが、審判例は分かれています。
審判では、全体の遺産総額によっては、生命保険金や死亡退職金について実質的公平の見 地から特別受益にあたるとしたものもあります(大阪家裁 昭和51年11月25日など)。また、保険科の支払などがあって、生存中その財産から何らかの支払いがあったことから生命保険金・死亡退職金について特別受益にあたるとしたものもあります。(福島家裁 昭和55 年 9 月16日)。
しかし、これらは生活保障のために付与されていて、相続分とは別に取得しても公平に反しない、むしろ亡くなった方(被相続人)の通常の意思に沿うと思われることなどを理由に、特別受益にあたることを否定した審判例が多くあります(東京家裁 昭和55年2月12日、東京高判平成10 年 6 月29日など)。
弁護士としては、最近の東京高等裁判所の決定がありますし、原則としては特別受益とならないと考えていたほうがよいだろうと思われます。 このように考えが分かれる問題でもあるので、調停では折衷的解決も可能なこともあるでしょう。
特別受益者の範囲は?だれが特別受益者なのか?
代襲相続人
代襲相続人も特別受益者になるのか?という問題があります。
① 被代襲者が特別受益を受けていた場合
これは、代襲した以上、持戻をするべきであるという見解が有力です。
審判例では、代襲相続人が被代襲者の特別受益によって現実に経済的利益を受けている場合に限りその限度で持戻しをさせるべきとして、被相続人が払っていた被代襲者の外国留学の費用について代襲相続人の持戻義務を否定したものがあります(徳島家庭裁判所 昭和52年3月14日)。
② 代襲者自身が直接特別受益を受けた場合
共同相続人間の実質的公平を図る見地から、特別受益者は、相続開始時に共同相続人となっていれば、その受益がいつ起きようとも、持戻義務を負うと考えられます(鹿児島家裁 昭和44年6月25日)。
もっとも、襲相続人のまえの相続人(被代襲者)がもらったものについてはで持戻さないという考えもあります。つまり、相続人となった後に受けたもののみ特別受益になるので持戻義務を負うという考えです。(大分家庭裁判所 昭和49年 5 月14日)。
包括受遺者
包括受遺者は相続人ではないのに、一定の割合の相続分を遺言でもらっているひとです。民法は「相続人と同一の権利義務を有する」としているので、持戻義務があるようにもおもえますが、被相続人としては、せっかく遺贈でべつに遺産をわけようとしているのですから、持戻しまでは予定していないのが通常であると考えられますので、持戻義務はないと考えるべきでしょう。
その他の人(間接的な受益者)
相続人がその配偶者や子の特別受益を通じて間接的に経済的利益を受けていることは結構ありますね。孫がたくさんの学費を払ってもらっていたような場合、その親の相続分まで影響するのかということです。
審判例としては、相続人の配偶者に生前贈与がなされた事例では、贈与の経緯、価値、性質、これにより相続人が受けている利益などを考慮し、実質的には相続人に直接贈与されたのと異ならないと認められるときは、相続人の特別受益と同視できるとして、持戻義務を肯定したものがあります(福島家庭裁判所 昭和55年 5 月24日)。
通常は、間接的受益者まで含めることはないと思われますが、上記のような場合、実質的に見て相続人がもらったのと同じようにみえる事案もありますので、そういった事案ではそれぞれの代理人弁護士が、事案ごとに主張を事実経緯とともに整理してなすべきでしょう。
特別受益はいくらになるのか?
いつを基準として評価するのか(特別受益の評価の基準時)?
過去になされた贈与ですが、象物の相続開始時の評価額にひき直しすとされていますので、基準時は亡くなった時点となります。もっとも、現実に遺産を分配する際の、遺産自体の評価については遺産分割時説が用いられています。
贈与されたものがもうない場合
もらった不動産はもう売ってしまったとか、自動車はもう破損してまって処分したというようなとき、どうするのでしょうか?
贈与当時には1000万円のマンションをもらっていて、1500万円ですでに売った時には、そのマンションが贈与当時の状態のままであるものと仮定して、死亡時(相続開始時)の価格を査定していきます。破損してしまった自動車も死亡時の価値(死亡時にまだ新車に近いならその価格になります。)を査定します。
もらったものの評価はどうするのか?
金銭をもらっていたら?
50年前の500万円は今の500万円と価値が異なりますよね。
よって、インフレ、物価上昇を考慮して、その実質的価値を相続開始時の貨幣価値に換算評価すべきであるとされていて、最高裁もこの考えをとっています(昭和51年3月18日判決)。
現金の贈与の事件ですが、消費者物価指数の変化に甚づき、総理府統計局消費者物価指数をつかって、相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価するべきであるとしたものがあります(広島高等裁判所の平成5年6月8日)。
物価指数であれば中立的なので、それで換算して計算するという方法として、正当でしょう。
農地をもらったときの評価方法
農地の表かは、宅地転用の見込みがあるかによって、経済的な価値が異なるので、難しい問題になります。
宅地として転用が確定していたり、その可能性が高い場合には、宅地となった場合の金額を基礎に算定するのが正当でしょう。争いがあって価値が高い土地であれば、裁判所で鑑定評価をしてもらう必要が出てくるかと思います。